『甘い生活』の闇を暴く:フェリーニ、ローマ、そして人間の欲望(映画史に残る傑作?)ゴシップ、虚無、そして永遠の問い:『甘い生活』の世界
フェリーニ監督の傑作『甘い生活』。舞台は60年代ローマ、華やかなゴシップ記者マルチェロの刹那的な日々を描く。トレヴィの泉でのアニタ・エクバーグの象徴的なシーン、そして「パパラッチ」という言葉の誕生。虚無感と孤独、純粋さへの憧憬が交錯し、観る者に強烈な印象を与える。ラストシーン、少女のジェスチャーは何を意味するのか?半世紀以上経った今も、人間の生き方を問いかける不朽の名作。
転落の果て:虚無感と失われた希望
マルチェロの虚無感を救う少女のメッセージとは?
酔ったマルチェロには届かず、観客も理解不能。
映画の終盤では、主人公マルチェロが虚無感に苛まれ、自堕落な生活から抜け出せなくなります。
救いの手を差し伸べようとする少女との出会いも、彼には届きません。
人間の心の闇と救済の難しさを描いています。
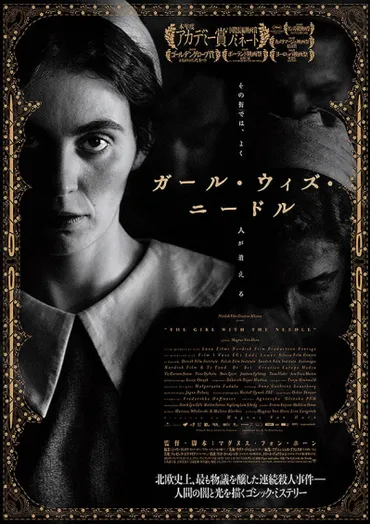
✅ NHK朝ドラ「ばけばけ」は、ハンバート・ハンバートの主題歌、川島小鳥のタイトルバック写真、美しい映像表現が高く評価されており、特に撮影と照明の技術が称賛されている。
✅ 脚本と演出はユーモアを交えつつも正統派の朝ドラとしての質を保っており、主演の髙石あかりの起用も作品の成功を確信させる要素となっている。
✅ 映画「宝島」は、大友啓史監督の力作だが、物語の中心人物の魅力が十分に描かれていない点と、終盤のゆっくりとしたテンポが評価を下げている。
さらに読む ⇒大江戸時夫の東京温度出典/画像元: http://oedo-tokio.cocolog-nifty.com/blog/cat1195271/index.htmlマルチェロが最後に見失う姿は、観る者に強烈な余韻を残しますね。
少女の存在が曖昧なまま終わるのも、救いの難しさを象徴しているように感じました。
マルチェロは文学への道を諦め、芸能人の宣伝マンとなりますが、最終的には目標を見失い、虚無感に苛まれます。
浜茶屋での出来事をきっかけに、自堕落な生活から抜け出せなくなるのです。
映画の終盤、マルチェロは美しい少女と出会い、彼女が何かを伝えようとしますが、マルチェロは酔っていて理解できません。
この少女は天使であり、マルチェロたちを優しく見守り、彼らの背中を見送ります。
観客は、少女のジェスチャーから何かを理解しようとしますが、結局はマルチェロと同じように、彼女の真意を完全に理解することはできません。
うむ、人間の業というものは、かくも深いものよ。マルチェロのように、目標を見失い、虚無感に苛まれるのは、現代社会においても普遍的なテーマと言えるでしょう。救済の道は、そう簡単には見つからないものですね。
リメイクの可能性:新たな視点と舞台
バブル期の日本版リメイク、何が映像の鍵?
派手さと虚無感、孤独を表現する映像技術。
映画『甘い生活』は、リメイクの可能性についても議論されています。
バブル期の日本を舞台にした短縮版という提案もあるようです。
作品が持つ普遍的なテーマは、時代や場所を超えて、人々の心に響くでしょう。
公開日:2015/01/11

✅ 映画「甘い生活」で一躍有名になったスウェーデン人女優アニタ・エクバーグさんが、83歳でイタリア・ローマで死去しました。
✅ 1951年にミス・スウェーデンに選出され、ハリウッドでモデル活動後、映画に出演。「甘い生活」では、トレビの泉での入浴シーンなどで世界的に知られるようになりました。
✅ イタリア映画を中心に活躍し、グラマラスな体で人気を博しましたが、スウェーデンでは評価されず、現地記者との対立もありました。
さらに読む ⇒ハフポスト - 日本や世界のニュース、会話を生み出す国際メディア出典/画像元: https://www.huffingtonpost.jp/2015/01/11/anita-ekberg-passed-away_n_6453078.htmlリメイクの話は面白いですね。
バブル期の日本を舞台にするというのは、確かに相性が良さそうです。
ただ、オリジナルの持つ陰鬱な雰囲気は、再現が難しいかもしれません。
映画のリメイクの可能性について、バブル期の日本を舞台にした短縮版が提案されています。
パーティーシーンの派手さと、その後の虚無感を強調し、主人公の孤独と、純粋な世界への憧憬を映像技術で表現することが可能であると示唆されています。
戦後のローマという舞台設定に疑問を呈し、経済力の差からハリウッドの方が相応しいという見解もある一方、映画が持つ普遍的なイメージは、主人公マストロヤンニの陰鬱な表情と相まって印象的です。
派手な生活への憧れを抱きつつも、自身は質素な生活を送ってきた経験が語られ、アニタ・エクバーグの存在感が称賛されています。
うーん、リメイクって、なんかちょっと難しいかな?でも、もしやるなら、今の技術でどこまで表現できるのかは、ちょっと興味あるかも!
永遠の問い:救いの道と観客の視点
映画『甘い生活』、ラストシーンの意味とは?
観客も理解できない、救われない人々の姿。
映画は、人間の生き方について深く考えさせられる作品です。
ラストシーンは、観客自身もまた、マルチェロと同じように、救いの道に気づけない存在であることを示唆しているとも解釈できます。
作品は、今もなお、多くの人々に影響を与え続けています。
公開日:2017/06/21

✅ 映画『甘い生活』は、冒頭のキリスト像とブルジョア婦人のシーンで、過去と現在、聖と俗の乖離を表現し、コミュニケーションの不可能性を描いている。
✅ 物語は、作家志望の主人公マルチェロがゴシップ記者として生きる中で、女性関係や仕事への理想を追い求める姿を描き、各挿話がマルチェロには幸福をもたらさず、最終的に少女の声も届かない「通行不可能性」を象徴している。
✅ 「声」を媒介とするコミュニケーションの失敗を描きつつ、初期作品『道』に見られるような、断絶の先にある別の次元での伝達の可能性を示唆しており、ラストシーンのマルチェロの微笑みには絶望と安らぎが入り混じった感情が込められている。
さらに読む ⇒ 総合文学ウェブ情報誌 文学金魚 ― 小説・詩・批評・短歌・俳句・音楽・美術・骨董・古典・演劇・映画・TV出典/画像元: https://gold-fish-press.com/archives/28064ラストシーンの解釈は奥深いですね。
観客もまた、少女の言葉を理解できないというのは、示唆的です。
映画は、観る人それぞれの解釈を許容する、懐の深い作品だと感じました。
映画は、マルチェロを見送った後、少女の視線が観客へと移り、フェードアウトすることで終わります。
このエンディングは、救いの道に気づけない人々の姿を描いているとも解釈できますが、観客自身もまた、彼女の言葉を完全に理解できないという意味で、マルチェロと五十歩百歩の関係にあると示唆しています。
映画『甘い生活』は、半世紀以上経った今でも、人間の生き方について深く考えさせられる作品として評価されており、そのロケ地は、今もなお多くの人々を魅了し続けています。
映画って、ほんま奥深いなぁ。最後のシーン、わてもよーわからんかった。でも、それがええんやろな。色んなこと考えさせてくれるもんな。
人間の欲望、虚無、そして救い。
映画『甘い生活』は、私たちに永遠の問いを投げかける傑作でした。
💡 映画は、1960年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞し、その映像美とテーマ性で世界を魅了したこと。
💡 「パパラッチ」という言葉を生み出し、その後の映画史に大きな影響を与えたこと。
💡 人間の内面の闇、虚無感、そして救いの難しさを描き出した作品であること。


