崇仁地区の今と未来?京都市立芸術大学移転とまちづくり、差別問題からの再生を問う?京都市崇仁地区:歴史、差別、そして再生への挑戦
京都・崇仁地区。差別と貧困の歴史を乗り越え、再開発が進む街で、芸術大学の移転が新たな風を吹き込む。学生たちは住民との交流を通して、過去と現在を作品に。思い出の詰まった街への愛着と、未来への希望が交錯する中で、アートが街を変える。地域住民と学生が共に歩む、文化と希望が生まれる物語。
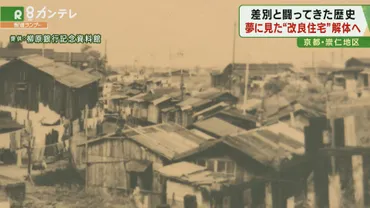
💡 長年差別を受けてきた崇仁地区で、京都市立芸術大学の移転を機に、地域再生の取り組みが始まっています。
💡 住民の住み慣れた地域への愛着と、大学移転への複雑な思いが交錯し、多様な価値観が生まれています。
💡 学生たちの活動や文化芸術によるまちづくりを通して、地域と大学が連携し、新たな未来を創造しようとしています。
それでは、京都の崇仁地区における歴史的背景、住民の思い、そして未来への展望について、詳しく見ていきましょう。
崇仁地区の歴史と現状
崇仁地区はどんな歴史を歩んできたの?
差別と孤立の歴史
本章では、崇仁地区の歴史と現状について深掘りしていきます。
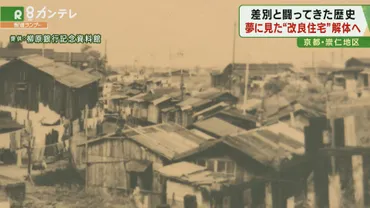
✅ 崇仁地区は、長年「差別」に苦しんできた歴史を持つ街で、住民は劣悪な住環境の中で生活してきました。高橋さんをはじめとする住民は、京都市に改良住宅の建設を求める運動を行い、1956年に実現しました。
✅ しかし、2023年度に京都市立芸術大学が移転する計画に伴い、改良住宅は取り壊されることになりました。住民は新築された公営住宅への引っ越しを迫られていますが、住み慣れた場所への愛着や、京都市の対応への不満から、引っ越しを望まない人も多くいます。
✅ 一方、片岡さんのように、街の変化を前向きに捉え、新しい出会いや街の活性化に期待する住民もいます。崇仁地区は、歴史や住民の思いを大切にしながら、新たな章を迎えようとしています。
さらに読む ⇒関西テレビ放送カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/191210/崇仁地区の歴史は、差別と貧困という深い影を落としてきました。
しかし、住民たちの粘り強い運動が改良住宅の建設を実現させました。
移転問題は、地域の歴史と未来に対する複雑な感情を呼び起こしています。
京都市下京区の崇仁地区は、長らく差別的な扱いを受けてきた地域であり、室町時代には鴨川河原の刑場に関わって被差別民が集まり始めました。
江戸時代には「穢多」と呼ばれる被差別階級の人々が住み、皮なめしなどの仕事に従事していました。
明治以降は在日コリアンがバラック小屋を建てて住むようになり、周辺住民との交流はほとんどありませんでした。
東海道新幹線や東京オリンピック開催時には、地区の景観が外部に知られないように対策が取られるほど、タブー視されていました。
近年では再開発が進められていますが、インフラ整備の遅れや住民の高齢化など、課題も多く抱えています。
うーん、差別の歴史って聞くと、なんか心が苦しくなるね。でも、住民の人たちが頑張って、自分たちの場所を守ってきたんだって思うと、すごいなって。
変革期を迎える崇仁地区の住民たち
崇仁地区の住民たちは、どんな状況に直面しているのでしょうか?
住居の取り壊し
本章では、変革期を迎える崇仁地区の住民たちの思いに焦点を当てます。
公開日:2020/07/19

✅ 記事は、千葉県で発生した中学生による殺人事件についてであり、被害者は84歳の女性で、容疑者は無差別な襲撃を行った可能性があることを伝えています。
✅ 記事は、中国が600年前の地図を根拠に主張している領土問題について、その危険性を指摘しています。中国は、歴史的な地図を武器として領土要求を行っており、これが国際的な紛争の火種となる可能性があると警告しています。
✅ 記事は、日本の財政問題を取り上げており、財政ポピュリズムが日本経済を破綻させる可能性を指摘しています。財政ポピュリズムとは、国民に人気のある政策を優先し、財政の健全性を無視する政策であり、日本の財政状況が悪化する原因の一つであるとされています。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/graphs/20200717/hpj/00m/040/002000g/20200717hpj00m040016000q住民たちの多様な思いが交錯する中で、高橋さんのような愛着と、片岡さんのような未来への期待が描かれています。
大学移転は、変化への挑戦であり、新たな出会いを生む可能性も秘めています。
1956年、崇仁地区の住民運動によって「改良住宅」が建設されました。
しかし、3年後には京都市立芸術大学の移転計画により、高橋さんが住む建物を含め7棟が取り壊されることが決定し、住民は新築された公営住宅への引っ越しを迫られました。
高橋さんは、思い出の詰まった住み慣れた場所への愛着から、新居への引っ越しをためらっています。
一方、片岡美佐代さんは、街の変化を前向きに捉え、大学移転による新しい出会いを期待しています。
なるほどね〜、住み慣れた場所を離れるのは寂しいけど、新しい出会いとか、街が活性化するっていうのは、ちょっと楽しみやな!
次のページを読む ⇒
京都市立芸術大学生が崇仁地区で地域住民と交流。廃材ベンチや郷土料理レシピ、地図で街の記憶を記録。差別問題の歴史を学び、芸術で街を変える可能性を探る。

