カレー沢薫が語る『モテるかもしれない。』は、一体どんな内容?カレー沢薫のモテるための処方箋とは!!?
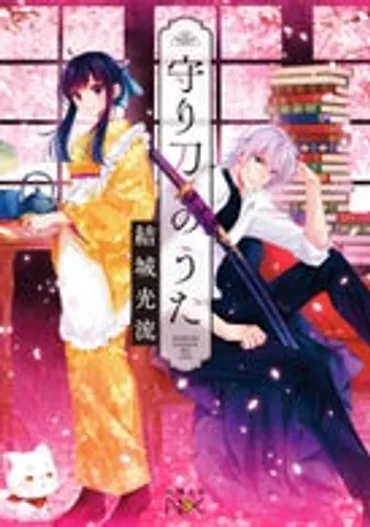
💡 カレー沢薫氏が考える「モテる」とは、単に異性から好かれることではなく、人間に好かれる力であるという考え方について解説します。
💡 さまざまな人物やキャラクターの行動分析を通して、計算や努力では得られない「モテる」秘訣を探ります。
💡 本書では、モテるための具体的テクニックではなく、個性や魅力を活かすことの重要性を説いています。
それでは、第一章から見ていきましょう。
モテることは計算や努力では得られない?カレー沢薫が語る『モテるかもしれない。』
カレー沢薫氏の独特な視点で書かれた本書は、多くの読者に共感を与えているようです。
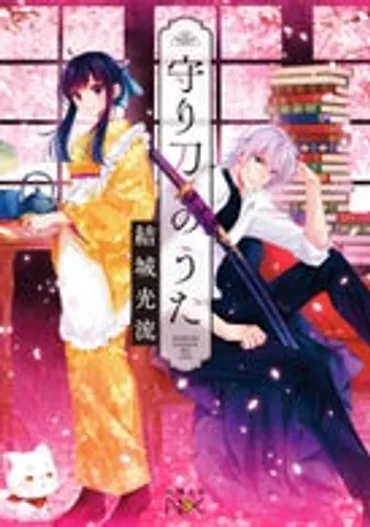
✅ 「モテ」とは、単に異性から好かれることではなく、「人間に好かれる力」であり、人間社会で生きていく上で重要な要素である。
✅ EXILEから西野カナ、アニメキャラクター、さらにはAV男優に至るまで、様々な「モテる」人の特徴を分析し、その秘訣を探る。
✅ 「モテたい」という願望を隠しながらも、実は多くの人が「モテ」に興味を持っていることを前提に、具体的な事例を交えながら「モテる」ための方法論を考察する。
さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000201.000047877.htmlカレー沢薫氏の分析力には脱帽ですね。
カレー沢薫氏は、自称「モテに失敗したコラムニスト」として、モテる人の特徴やモテ方について独自の視点で考察した書籍『モテるかもしれない』を執筆しました。
本書は、モテるテクニックを紹介するのではなく、モテる人の行動や特徴を分析することで、読者に新たな視点を与え、人生を変えるヒントを提供しています。
カレー沢氏は、EXILE、バーフバリ、安室透、売れっ子AV男優、ジブリ作品に登場する男性キャラクター、乙女ゲームのイケメンキャラクターなど、様々な人物やキャラクターから学びを得ようとします。
その過程で、モテることは計算や努力、優勝によって達成できるものではなく、個性や魅力を活かすことが重要であるという結論にたどり着きました。
本書は、モテることに固執するのではなく、自分自身の魅力や個性を受け入れることで、自分らしく生きることができるというメッセージを伝えています。
へぇー、モテるって努力じゃなく、個性なんだー。
絵の腕前に対するコンプレックスと自己肯定感
カレー沢薫氏は、自身の創作活動に対するコンプレックスと向き合うことで、自己肯定感の重要性について深い考察をしています。
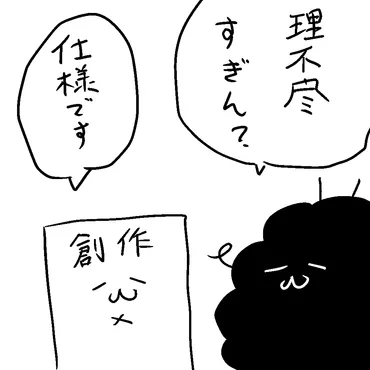
✅ この記事は、1年かけて描いた漫画が、同じジャンルの人のらくがきに評価で負けてしまったという相談者の悩みについて、創作活動における劣等感と努力の価値について考察しています。
✅ 作者は、創作の世界では、努力だけでは結果が得られない理不尽な部分があること、しかし、才能のある人でも努力を重ねてきたことを指摘し、相談者も努力を続けるべきだと励ましています。
✅ さらに、努力よりも看板や才能が重視されているように見えるのは、その看板や才能を得るために、目に見えない努力や苦労があったことを忘れてはいけないと、相談者に客観的な視点を持つことを促しています。
さらに読む ⇒1年かけたマンガが、らくがきに負けた」上を見るよりも自分の評価を見る /カレー沢薫の創作相談出典/画像元: https://www.pixivision.net/ja/a/8044カレー沢薫氏のように、努力を重ねても結果が出ないことがありますよね。
カレー沢薫氏は、自身の絵の腕前に対するコンプレックスについて、他人の評価とのギャップに苦しむ様子を描いています。
友人に「あなたが描いたものかと思った」と言われたことで、自身の絵の腕前に疑問を抱き、創作意欲を失ってしまったという悩みを語ります。
作者は、このコンプレックスは他人の評価に過敏になり、自分の能力を過小評価してしまうことによって生じるものだと分析しています。
そして、コンプレックスの克服には時間がかかるものの、加齢とともに自己肯定感が増し、他人の評価に左右されなくなる傾向があることを指摘しています。
年齢を重ねることで、自分の個性や価値観を大切にするようになり、他人の評価に囚われずに自分の道を歩む重要性を理解するようになると締めくくられています。
うちも絵描くけど、全然上手くないし、先生に褒められたことないねん。
学生時代の「優等生」という幻想
作家という職業を通して、会社員とは異なる働き方の視点が語られています。
公開日:2022/04/06

✅ カレー沢薫氏は、作家という仕事の特性から、会社員とは異なる「病(ビョウ)」という表現を用いて、仕事に対する独特な見方を展開しています。
✅ 作家は、連載終了や新しい連載開始を繰り返すため、会社員で言うところの「会社が倒産して転職を繰り返す」ような状況にあり、常に新しい環境に適応する必要があり、安定した環境を求める会社員とは対照的な立場にあると説明しています。
✅ コロナ禍によりリモートワークが普及したことで、会社員の働き方もフリーランスと似てきた一方で、新入社員は、慣れた先輩社員のサポートがない状況で、不安定な状況に置かれているという現状を指摘しています。
さらに読む ⇒マイナビニュース出典/画像元: https://news.mynavi.jp/article/cheerful-curry-293/会社員時代、苦手なことを無理して続けてきたという経験は、多くの人が共感するのではないでしょうか。
カレー沢薫氏は、生まれつき得意不得意があり、苦手なことを克服するより、得意を生かせる方向に進むべきだと主張します。
しかし、著者は会社員時代、自分に合っていない仕事に就き、無駄な時間と苦しみを経験したと語ります。
これは、著者が「自己分析能力」に欠けていたためであり、適切な職業選択ができなかった結果だと分析します。
著者は、学生時代は周囲に迷惑をかけずに過ごしていたが、社会人になってから問題が噴出し、居場所を失った経験から、学生時代の「優等生」という評価が誤っていた可能性に言及します。
学校ではテストの点数で評価されるため、テストの点数だけは良い何もしない生徒は誤って「優等生」と見なされてしまうことがあると指摘します。
しかし、会社では「周囲と馴染まない」や「何もしない」は大きな問題となる。
著者は、学生時代は問題児と見なされず、誤って「優等生」と見なされてしまったため、社会人になってから自分の能力や適性を見誤ったと結論付けます。
学生時代は、テストの点数がすべてだと思ってたわ。
インタビューという試練
カレー沢薫氏は、インタビューという試練に対して、独特な考え方を持っています。

✅ この記事は、在宅ワークにおける必需品として「パソコン」の重要性を説いています。
✅ パソコンは、漫画家やライターにとって原稿作成のデジタル化を可能にし、紙媒体による原稿作成に伴う様々な問題点(汚れ、劣化、修正の困難さなど)を解消する役割を果たしています。
✅ 作者であるカレー沢氏は、自身のアナログ作画の苦手さや注意力散漫さを例に挙げ、パソコンがなければ原稿作成は不可能であったと断言しており、その重要性を強調しています。
さらに読む ⇒株式会社 PFU出典/画像元: https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/digiup/article/scansnap/00239/インタビューを受けることは、誰にとっても緊張する場面ですよね。
漫画家・コラムニストのカレー沢薫氏は、インタビューに対する独特な見解を述べています。
デビュー以来、インタビューを受けた経験はほとんどなく、むしろ幻聴のように感じていたといいます。
しかし、近年は社会派を気取りだしたせいか、インタビュー依頼が急増し、コロナ禍でリモートワークが普及したことで、Zoomなどのビデオ会議ツールを使ったインタビューが増えたと語ります。
氏は、リモートワークによってインタビューが「手軽」になった一方で、以前のようにわざわざ相手のもとへ赴いてインタビューする意味が分からなくなったとも述べています。
インタビューは、マジメに答えるとつまらない話しかできず、ふざけると「おもしろくない上に周囲ドン引き」になってしまうため、氏にとっては難しい課題であると語ります。
インタビューって、なんか緊張するよねー。
カレー沢薫氏の独特な視点で、人生の様々な側面を考察した本書は、読者に多くの気づきを与えてくれます。
💡 「モテる」とは、人間に好かれる力であり、個性や魅力を活かすことが重要である。
💡 努力だけでは結果が出ないこともあるが、努力することの価値は大きい。
💡 学生時代の「優等生」という幻想に囚われず、自分の能力や適性を理解することが重要である。


