『死ねない理由』:貧困脱出と文化体験、生きることの意味とは?ヒオカさんの実体験から紐解く!!
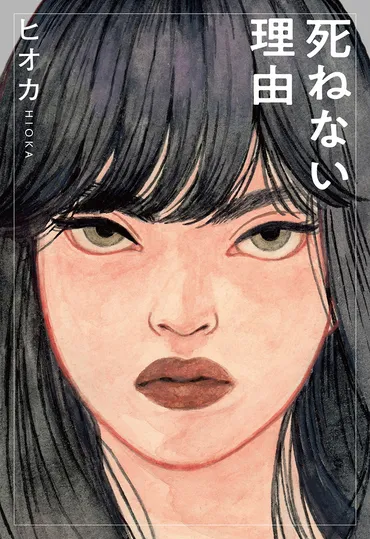
💡 貧困家庭出身の女性ライターが、自身の経験を通して「生きる」ことについて考察したノンフィクション作品です。
💡 貧困家庭出身の著者が、奨学金を活用して大学へ進学し、ライターとして世に出るまでの道のりを描いています。
💡 著者は、自身の経験を通して、経済的な豊かさだけでなく、文化的な豊かさも人間にとって不可欠であることを主張しています。
それでは、第一章へ進みましょう。
「死ねない理由」:貧困からの脱出と文化体験の重要性
本書は、経済的な困窮だけでなく、心の葛藤や自己肯定感の低さなど、様々な苦悩が描かれており、読み手の心に深く響く作品だと思います。
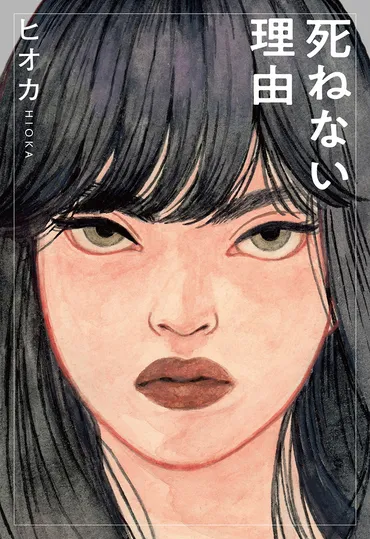
✅ 「死ねない理由」は、地方の貧困家庭で育った著者が、奨学金を受けて大学へ進学し、ライターとして世に出るまでの道のりを描いたノンフィクション作品です。
✅ 著者は、安定した職に就けず、常に金銭的不安を抱え、原因不明の体調不良に悩まされ、世間からのプレッシャーにも苦しむ中、生きる意味を見いだす葛藤の日々を描いています。
✅ 本書は、著者のウェブ連載「貧しても鈍さない 貧しても利する」を基に、初の著書『死にそうだけど生きてます』出版後に経験したことを加筆したものです。
さらに読む ⇒中央公論新社出典/画像元: https://www.chuko.co.jp/tanko/2024/03/005768.html著者の言葉が、読者に希望を与えるとともに、自分自身を見つめるきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。
本書『死ねない理由』は、貧困家庭出身のフリーライターである著者が、自身の経験を通して「生きる」ということについて考察した作品です。
著者は、幼少期の家庭内暴力や学校でのいじめなど、困難な状況の中で「早く死にたい」と考える時期もありました。
しかし、大人になってからは経済的に安定し、好きなアーティストのライブに行くなど、文化的な活動を楽しむことができるようになりました。
本書では、「生きていくための経済的基盤」と「生きていくための文化的経験」の重要性を訴えています。
著者は、経済的格差によって文化的な体験が制限されている現状に課題を感じており、特に「貧困でも夢を諦めなくていい」というメッセージを発信しています。
著者は、自身の経験を通して、経済的な豊かさだけでなく、文化的な豊かさも人間にとって不可欠であることを主張しています。
そして、文化的な体験の機会が限られている人々に対して、夢を諦めずに、自分にとって大切なものを追求していくことの大切さを伝えています。
ほな、金持ちしか文化体験できへんのか?貧乏人は、文化体験するな、って言うてるんか?
貧困の連鎖:想像力への影響と子供の貧困
貧困によって、想像力や選択の幅が制限されるという現状は、非常に深刻な問題だと思います。
公開日:2024/07/28

✅ 「死にそうだけど生きてます」は、著者のヒオカさんの貧困家庭での体験談を通して、格差問題の現実を浮き彫りにする衝撃的な内容の本です。
✅ 著者は、自分の経験を通して、格差問題は想像力不足が原因であるとし、他者への想像力を育むことの重要性を訴えています。そのためには、異なる環境の人々に目を向けるための「知ること」が必要だと説いています。
✅ 著者は、貧困家庭の現状を深く理解するために、ヒオカさんの著書「死にそうだけど生きてます」を読むことを推奨しています。この本は、読者に想像力を育むきっかけを与え、社会に対する理解を深める助けとなるでしょう。
さらに読む ⇒あたまの中は無印出典/画像元: https://atama-muji.com/shinisoudakedo/本書は、貧困の連鎖が、子供たちの未来を閉ざしてしまう可能性を示唆しており、社会全体で解決策を探していく必要があると感じました。
ヒオカさんの著書『死ねない理由』は、前作『死にそうだけど生きてます』に続く、貧困状態から脱出後の日常を描いたエッセイです。
貧困は、子供時代に経験する機会の少なさから想像力や選択の幅に格差を生み出し、大人になっても続く負の連鎖をもたらすことがわかります。
ヒオカさんは、貧困状態では、当事者自身が自分の状況に気づきにくい現状を指摘します。
周りの人と比べて初めて、自分の貧困に気づく場合もあるでしょう。
しかし、同じような環境の友達ばかりの中で育つと、客観的な比較がなく、貧困状態に気づきにくくなります。
著者は、想像力も努力だけではどうにもならない部分があり、想像力を責める側もまた、想像力不足かもしれないと述べています。
子供の貧困は、大人になって解決できる問題ではなく、子供時代の経験がその後の人生に大きな影響を与えることを、本書は深く考えさせます。
想像力は、人生の航海における羅針盤のようなものです。貧困は、その羅針盤を壊してしまう可能性を秘めていると言えるでしょう。
葛藤の日々:経済的不安と社会からのプレッシャー
著者が、貧困や社会からのプレッシャーに苦しみながらも、生きようとする姿は、とても感動しました。
公開日:2023/01/20

✅ 筆者は、推しに出会うことで「生きる意味」を見出し、死んでしまいたいと思っていた過去から、推しをもっと見たいという強い意志を持って生きるようになった。
✅ 特に、ちゃんみなさんの生き様や表現に感銘を受け、自分自身も表現することを楽しむようになり、人生を楽しむようになったと語る。
✅ 推しを推すことは、筆者にとって生活の安定をもたらすだけでなく、生きがいを見つけるきっかけとなり、本当の意味で生きている実感を得ることに繋がったと結論付けている。
さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/7522?page=3生きることが難しい状況の中でも、希望を見出し、前に進む著者の強い意志を感じます。
「死ねない理由」は、地方の貧困家庭で育ち、奨学金で大学に進学した著者が、ウェブで発表した記事が注目を集め、ライターとして世に出た後、常に金銭的不安を抱え、体調不良に悩みながらも生きようとする葛藤を描いた作品です。
著者は、初の著書『死にそうだけど生きてます』出版後、安定した職に就けず、世間からの「貧困者は身の程を知れ」というプレッシャーにも苦しんでいます。
本書では、「婦人公論jp」連載「貧しても鈍さない貧しても利する」を中心に、自身の経験を綴り、生きる意味を見いだす葛藤の日々を赤裸々に描写しています。
私も、好きなアイドル見てると元気になる!推しがいると頑張れるよね!
トークイベント:貧困とファッション、異なる家庭環境への共感
このイベントを通して、貧困問題に対する理解が深まりました。

✅ 坂口涼太郎さんはヒオカさんの著書「死にそうだけど生きてます」を読んで、貧困はヒオカさんだけの問題ではなく、世の中に多く存在する問題だと気づき、衝撃を受けたことを語りました。
✅ ヒオカさんは現在も生活は余裕がないものの、以前のように極度の貧困状態からは抜け出しており、エンタメを楽しむ余裕も出てきていることを伝えました。
✅ 坂口涼太郎さんは、エンタメが生活に困っている人々にとっても必要なものであり、エンタメを提供する立場として、そのような人々にエンタメを届けることを重要だと考えていることを語りました。
さらに読む ⇒mi-mollet(ミモレ) | 明日の私へ、小さな一歩!出典/画像元: https://mi-mollet.com/articles/-/48797?layout=bエンタメが、人々にとってどのように癒しや希望を与えているのか、改めて考えさせられる内容でした。
ライターのヒオカさんと俳優の坂口涼太郎さんのトークイベントが、2024年5月1日に東京・代官山蔦屋書店で開催されました。
イベントは、ヒオカさんの新刊『死ねない理由』と坂口さんの「ミモレ」連載開始を記念し、それぞれの作品に込めた思いや、「書く」ことについて語り合いました。
ヒオカさんが坂口さんのWEBサイト『ミモレ』で取材をしたことがきっかけで、今回のイベントが実現。
2人のファッションセンスについても話題となり、坂口さんは「お洒落にお金はいるのか?」という問いに「貧困から世に出ていくと、最低限に生活しろ、っていうSNSなどの圧がありますよね。
柚木麻子さんに〈グッチを着て貧困を語ればいい〉って言われたんです」と自身の経験を踏まえて答えました。
坂口さんの連載は、ヒオカさんの提案から実現。
自宅での撮影の様子や、撮影後に手作りの豚汁を振る舞ったエピソードなどが語られました。
坂口さんは『死ねない理由』を読んで、自身とは異なる家庭環境を持つ人たちの存在に衝撃を受けたことを明かし、ヒオカさんは単行本化にあたって、連載では書けなかった内容を詰め込んだと語りました。
貧乏でも、お洒落したら、ホンマに金持ちに見えへんねんか?
貧困は、個人の問題ではなく、社会全体で解決すべき課題であることを改めて認識しました。
💡 貧困家庭出身の著者が、自身の経験を通して、貧困の現状や生きることの意味について考察しています。
💡 本書は、経済的な豊かさだけでなく、文化的な豊かさも人間にとって不可欠であることを訴えています。
💡 貧困は、想像力を奪い、子供の未来を閉ざしてしまう可能性もあることを示唆しています。


