桂雀々、上方落語の未来を担う!?上方落語界の異才とは!?
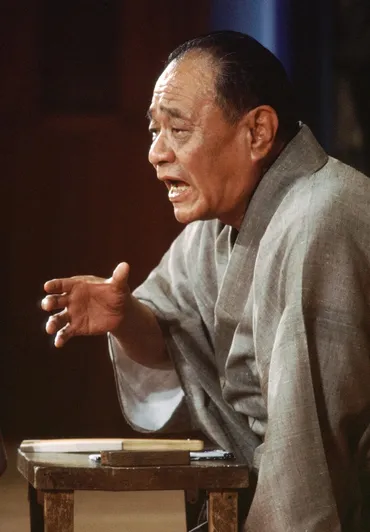
💡 上方落語の歴史と発展について解説します。
💡 桂雀々さんと筆者の出会いを振り返ります。
💡 桂雀々さんの魅力と功績について考察します。
それでは、桂雀々さんの生涯と上方落語について詳しく見ていきましょう。
上方落語の歴史
上方落語の歴史は、まさに波乱万丈ですね。
公開日:2019/07/12
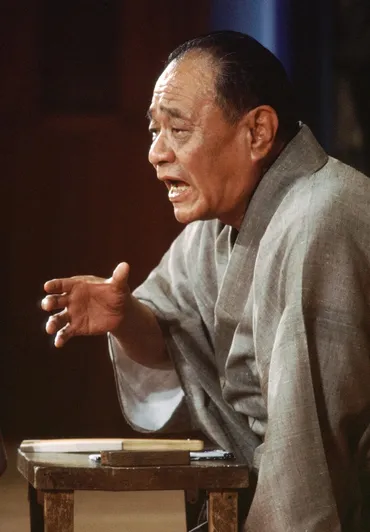
✅ 上方落語は江戸時代元禄時代に始祖が誕生し、寛政時代に寄席が誕生して発展しました。明治時代には桂派と三友派が隆盛を極めましたが、昭和初期には漫才の台頭に伴い衰退しました。
✅ 戦後、上方落語は復興の道を歩み、昭和28年には「大阪落語倶楽部」が発足し、昭和32年には「上方落語協会」が設立されました。
✅ 上方落語協会は、上方落語の保存と継承を目的とし、若手落語家の育成や公演活動などを行ってきました。現在も上方落語は伝統芸能として発展を続けており、新たな時代に向けて更なる発展が期待されています。
さらに読む ⇒公益社団法人 上方落語協会出典/画像元: https://kamigatarakugo.jp/history/上方落語は、長い歴史の中で多くの変化を遂げてきたんですね。
上方落語は、元禄時代に露の五郎兵衛と米澤彦八が神社境内などで滑稽な話を演じたことから始まりました。
その後、寛政時代に初代桂文治が寄席を開設し、笑福亭、林家、月亭などの落語家が台頭しました。
明治時代には桂派と三友派が隆盛を極めましたが、大正時代には吉本興行部が演芸界を統一しました。
昭和初期には漫才中心となり落語は衰退しましたが、五代笑福亭松鶴らによって「楽語荘」が結成され、上方落語の保存と継承活動が始まりました。
戦後の復興期には、昭和20年11月に四天王寺本坊客殿で戦後初の落語公演が行われました。
昭和22年には戎橋松竹が開場し、昭和24年には関西演芸協会が発足しました。
しかし、昭和25年から28年にかけて松鶴、春團治、花橘、米團治といった大物が相次いで亡くなり、上方落語は危機に瀕しました。
昭和28年には「大阪落語倶楽部」が設立され、昭和29年には戎松落語日曜会が再開、昭和30年には三越落語会とABC上方落語をきく会が始まりました。
これらの活動は、のちの四天王と呼ばれる若手落語家の活躍の基盤となりました。
昭和31年の若手落語家の忘年会では、親睦団体もしくは協会結成の機運が高まり、昭和32年4月12日に上方落語協会が設立されました。
創設当初は会員は18名で、会長には三代林家染丸、幹事には六代笑福亭松鶴、三代桂福團治、桂米朝、五代桂小文枝、三代旭堂小南陵が選ばれました。
同年5月4日には協会主催の「落語土曜寄席」が道頓堀文楽座で始まり、以後、京阪神で定期公演が開催されるようになりました。
昭和33年5月1日には道頓堀「角座」が開場し、上方落語協会は本格的な活動を開始しました。
歴史はええねんけど、よう分からんわ。
雀々との出会い
桂雀々さんとの出会いは、あなたの人生に大きな影響を与えたんですね。

✅ 桂雀々(当時松本少年)が、桂枝雀そっくりの口調で話す姿が、上沼恵美子のワイドショーで放映され、視聴者の心を掴んだ。
✅ 当時、浪人生だった筆者は、落語に熱中しすぎて親から「丁稚に行け!」と怒鳴られ、落語家への弟子入りを決意する。
✅ 筆者は、桂枝雀の弟子入りを志す中で、ワイドショーに出演した松本少年が、将来枝雀の弟子になり、自分もその弟弟子になるのではないかと想像し、印象深く見ていた。
さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/552de24d38b0a5f0d3ca161c7ed5b10f34651fb4ワイドショーでの雀々さんの姿、印象的だったでしょうね。
1976年か1977年、上沼恵美子のワイドショーで、枝雀そっくりの口調で話す少年桂雀々を見た。
彼は、落語家になりたく、枝雀の弟子になりたいと話していた。
少年は家に帰っても誰もいないため、生けてある花に話しかけるという話をし、上沼恵美子は涙を流しながら、枝雀に弟子にしてほしいと頼んだ。
当時、浪人生であった私は、親から「そんなんやったらもう大学なんか行かんと、丁稚に行け!」と怒鳴られ、落語家になることを決意した。
桂米朝か桂枝雀か迷ったが、高校時代の落語研究会の仲間のアドバイスもあり、枝雀の弟子入りを決意した。
そのワイドショーで見た少年が、枝雀の弟子入りを果たし、桂雀々となるのを見て、自分も弟子入りすれば、その少年の弟弟子になるのかもしれないとぼんやり考えていた。
その後、私は東京の大学へ進学し、少年は桂雀々として落語の世界へ進んだ。
若き日の雀々さんの姿が、すでに才能を感じさせますね。
雀々の魅力
雀々さんの落語は、ミュージシャンからも高く評価されているんですね。

✅ 桂雀々は、糖尿病による肝不全で亡くなったが、生前、根本要をはじめとする多くのミュージシャンと交流があり、その魅力は、従来の古典落語とは異なる、ロックやジャズのような自由で型破りなスタイルにあった。
✅ 雀々の落語は、従来の型にはまらず、自由にアレンジを加え、笑いを追求していたため、ミュージシャンたちから共感を得ていた。
✅ 根本要は、雀々の落語は、目をつぶって聴くのがもったいないほど魅力的で、その笑いにどん欲な姿勢は、根本自身も共感するものであったと語っている。
さらに読む ⇒BIGLOBEニュース出典/画像元: https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/1122/spn_241122_8510024882.html雀々さんの落語は、従来の落語とは全く違う魅力がありますね。
人気バンド「スターダスト☆レビュー」の根本要は、40年来の親友である故・桂雀々さんを悼み、その魅力をスポニチの取材で語った。
根本は、雀々さんが糖尿病で亡くなったことを信じられず、その生き様を「生きたいように生きる」と表現した。
雀々さんは、お酒を控えるように言われても、根本を飲みに行こうと誘うなど、最後まで明るく過ごしていたという。
根本は、雀々さんが山下達郎や桑田佳祐といったミュージシャンと親交が深かった理由について、雀々の落語がロックやジャズ的な要素を含んでいたからだと分析した。
雀々は古典落語を独自の解釈でアレンジし、型破りな笑いを追求していたため、根本は「一匹狼的なロック魂」を感じたと語った。
根本は、雀々の落語を「目をつぶって聴くのがもったいない」と評し、その才能がこれから開花していくところで亡くなったことを惜しんだ。
なんか、かっこいい言葉がいっぱい!
桂雀々さんの功績
雀々さんの功績は、落語界に大きな影響を与えましたね。
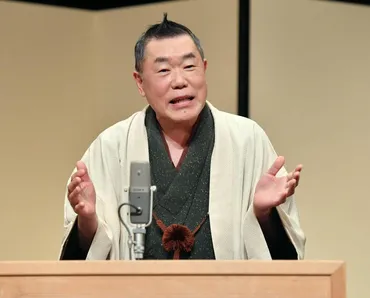
✅ 上方落語家・桂雀々さんが、肝不全のため64歳で亡くなりました。
✅ 雀々さんは、1977年に桂枝雀さんに師事し、07年には「桂 雀々独演会 雀々十八番」をシアターBRAVAで開催、全公演完売の大成功を収めました。
✅ 雀々さんは、11年に拠点を東京に移し、映画やドラマ、舞台などにも出演し、ドラマ「陸王」では嫌味な銀行支店長を演じ話題になりました。
さらに読む ⇒デイリースポーツ online出典/画像元: https://www.daily.co.jp/gossip/2024/11/23/0018371151.shtml雀々さんは、多岐にわたる分野で活躍されましたね。
落語家の桂雀々さんが、11月20日に64歳で亡くなりました。
所属事務所によると、死因は糖尿病からの肝不全とのことです。
桂雀々さんは1960年8月9日生まれ、大阪市住吉区出身で、本名は松本貢一です。
1977年に上方落語の桂枝雀に入門し、同年10月に初舞台を踏みました。
2007年には「桂雀々独演会雀々十八番」をシアターBRAVAにて6日間開催し、全公演完売の大成功を収めました。
2010年には「五十歳五十箇所地獄めぐり」を開始し、全国を行脚。
2011年には拠点を東京に移し、独演会は毎回完売となりました。
落語以外にも、テレビ、映画、舞台など多方面で活躍し、2017年にはドラマ「陸王」で嫌味な銀行支店長を演じ、話題になりました。
上方お笑い大賞最優秀技能賞(2002年)、大阪府舞台芸術賞奨励賞(2006年)などを受賞しています。
著書に「必死のパッチ」(幻冬舎)があります。
2013年にはBS12にて冠番組「桂雀々の大判小判がじゃくじゃく」がレギュラー放送され、2014年にはソニー「来福レーベル」よりDVD「桂雀々ええやん」が4巻同時発売されました。
桂雀々さんは、入院中も最後まで高座復帰を目指して療養に努めていましたが、願いは叶いませんでした。
ご遺族の意向により、葬儀は近親者のみで行われました。
後日、「お別れの会」が予定されています。
ドラマ「陸王」の銀行支店長、ほんまに嫌味な役やったわ。
雀々の遺産
雀々さんの残したものは、これからも多くの人に語り継がれていくでしょう。
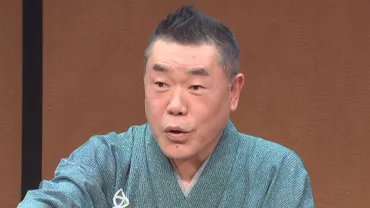
✅ 落語家の桂雀々さんが、糖尿病からの肝不全により、11月20日に64歳で亡くなりました。
✅ 所属事務所は、桂雀々さんが入院中も高座復帰を目指して療養に努めていたことを明かし、訃報とともに生前の活躍を称えました。
✅ 葬儀は近親者のみで行われ、後日「お別れの会」が予定されています。
さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1568640?display=1雀々さんの死は、落語界にとって大きな損失ですね。
桂雀々さんは、古典落語を独自の解釈でアレンジし、型破りな笑いを追求していました。
その才能は、多くの人の心を捉え、落語の世界に新たな風を吹き込みました。
彼の落語は、目をつぶって聴くのがもったいないほど、魅力的で、彼の生き様は、多くの人に感動を与え続けました。
彼の死は、落語界にとって大きな損失ですが、彼の残した作品は、これからも多くの人々に愛され続けるでしょう。
雀々さんの逝去は、日本の伝統芸能界にとって大きな痛手です。
桂雀々さんは、伝統芸能である上方落語を現代に蘇らせた、まさに伝説の人と言えるでしょう。
💡 上方落語の歴史、発展、そして桂雀々さんの功績について解説しました。
💡 桂雀々さんと筆者の出会いを振り返り、雀々さんの魅力について考察しました。
💡 桂雀々さんの遺産は、これからも多くの人に語り継がれていくでしょう。


