元NHKアナウンサー、内多勝康さんの転身! 医療的ケア児の支援に人生をかける?医療的ケア児への熱い思いとは!?
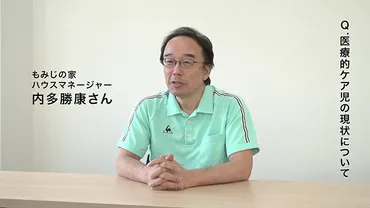
💡 元NHKアナウンサーの内多勝康さんが、医療的ケア児の支援に人生を捧げている。
💡 安定したキャリアを捨て、福祉の道へ転身した理由とは?
💡 医療的ケア児とその家族の現状、そして未来への希望について語ります。
それでは、内多さんの壮絶な人生の物語を、章ごとに紐解いていきましょう。
NHKアナウンサーから福祉の道へ
内多さんの決断には、深い思いが込められていると感じます。
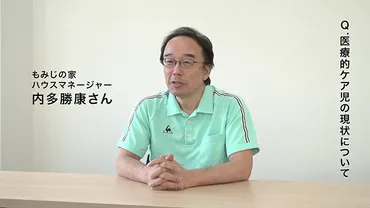
✅ 医療的ケア児の数は10年で2倍に増え、人工呼吸器を付けた子どもは10倍に増えている。これは、医療技術の進歩により、これまで助からなかった命が助かるようになった一方で、医療的ケアが必要な子どもが増えていることを示している。
✅ 医療的ケア児は、退院後も医療が必要なため、従来の医療と福祉の枠組みでは対応が難しい。もみじの家の運営を通じて、医療と福祉が融合した新しいサポート体制が必要だと実感している。
✅ 医療的ケア児の家族は、常に子どもの命を守る重圧の中で生活しており、ゆっくりと休む時間もない。もみじの家のような施設で子どもを預けることで、家族は心身ともに休むことができ、社会に現状を発信する機会も得られる。内多さんは、家族の声を社会に発信し、医療的ケア児のサポート体制の充実を願っている。
さらに読む ⇒大和ネクスト銀行出典/画像元: https://www.bank-daiwa.co.jp/tametalk/ouen/momijinoie_01.html医療的ケア児の家族が抱える負担の大きさがよく分かります。
内多さんのような人がいて本当に心強いです。
元NHKアナウンサーの内多勝康さんは、2016年52歳で医療的ケア児の短期入所施設「もみじの家」のハウスマネージャーに転職しました。
きっかけは、2013年に放送された「クローズアップ現代」で取り上げた医療的ケア児に対する支援の必要性でした。
内多さんは、番組制作を通じて医療的ケア児の課題を深く知り、その支援に携わりたいという強い思いを抱くようになりました。
その後、「もみじの家」の設立準備を知り、ハウスマネージャーの誘いを受け、転職を決意しました。
安定したNHKでのキャリアを捨て、福祉の現場への転身を決めたのは、仕事とやりがいを一致させたいという強い思いと、この機会を逃したら一生後悔するだろうという覚悟があったからです。
内多さんは、自身の経験を踏まえ、医療と福祉が連携し、子どもたちが「その人らしく生きる」ことを支援していくことの重要性を訴えています。
ほな、内多さん、NHK辞めてもええ暮らし出来てるんか?
アナウンサーとしてのキャリア
アナウンサー時代も、福祉分野に強い関心を持っていたんですね。

✅ 元NHKアナウンサーの内多勝康さんは、2016年に医療的ケア児の短期入所施設「もみじの家」のハウスマネージャーに転職しました。
✅ 転身のきっかけは、内多さんが2013年に「クローズアップ現代」で医療的ケア児を取り上げた番組を制作したことでした。
✅ 番組制作を通して医療的ケア児とその家族の課題を深く知った内多さんは、「もみじの家」の設立準備を進める成育医療研究センターからハウスマネージャーの誘いを受け、50代前半で転職を決意しました。
さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/relife/article/14478058内多さんの人生は、まさに「転換期」ですね。
NHKという安定した場所を離れてまで福祉分野に飛び込んだその決意に、敬意を表します。
内多さんは、大学卒業後、NHKに入局。
当初はディレクター志望でしたが、アナウンサーとして採用されました。
就職は貧しい生活からの脱却を目的としており、NHKの安定性を重視したそうです。
入局後、ディレクターへの転身は叶いませんでしたが、アナウンサーとして西日本で経験を積み、その道でやっていくことを決意しました。
高松局時代に、福祉タクシーの存続問題を取り上げた番組企画を提案し、制作に携わったことが、番組作りへの関心を深めるきっかけとなりました。
その後も、企画提案から構成、取材まで、アナウンサーの仕事に加え、番組作りにも積極的に関わるようになったそうです。
内多さんは、アナウンサーという枠を超えて、社会貢献を志したと言えるでしょう。
「クローズアップ現代」から社会福祉士へ
内多さんの社会福祉士への道は、まさに「クローズアップ現代」の物語ですね。
公開日:2018/12/06

✅ 元NHKアナウンサーの内多 潤さんが、医療的ケアを必要とする子供とその家族のための短期入所施設「もみじの家」のハウスマネージャーに転職した経緯と、現在の仕事に対する思いについて語られています。
✅ 「もみじの家」は、退院後も医療的ケアが必要な子供たちが安心して過ごせる施設として、イギリスの「ヘレン・ダグラス・ハウス」を参考に設立されました。
✅ 内多さんは、元々はディレクター志望でしたが、アナウンサーとして入社後も福祉分野の取材を続け、現在の仕事に至りました。アナウンサー時代には、福祉タクシーの存続や自閉症の男性に関するドキュメンタリー番組を通して、社会の側がどう環境を整えるのかという問題提起をしてきました。
さらに読む ⇒好書好日|Good Life With Books出典/画像元: https://book.asahi.com/article/11987819内多さんのように、社会課題に対して積極的に行動を起こす人が増えることを願っています。
元NHKアナウンサーの内多勝康さんは、2013年に「クローズアップ現代」で医療的ケア児を取り上げたことをきっかけに、その後の社会福祉士資格取得や「もみじの家」との出会いを通じて、自身の経験を社会貢献に活かしたいと考えるようになりました。
内多さんはNHKアナウンサー時代、「医療的ケア児」の問題を番組で取り上げましたが、30分の放送では社会課題の解決には至らなかったと感じ、社会福祉士の資格を取得しました。
その過程で「ソーシャルアクション」という言葉を学び、社会福祉士の役割は、困っている人への支援だけでなく、社会構造そのものに働きかけることだと認識しました。
50歳で社会福祉士資格を取得した内多さんは、医療的ケアが必要な子供とその家族を支援する短期入所施設「もみじの家」の存在を知り、その理念に共感し、アナウンサーを辞めてソーシャルアクションを仕事にすることを決意しました。
内多さんは「重い病気を持つ子どもと家族の一人一人がその人らしく生きることができる社会を作っていく」という「もみじの家」の理念に共感し、自身の経験と知識を活かして社会貢献をしたいと強く考えるようになりました。
内多さん、社会福祉士ってすごい!私も将来は社会に役立つ仕事がしたい!
医療的ケア児とその家族の現状
医療的ケア児と家族が直面する困難な状況が分かります。

✅ 医療的ケア児と家族は、支援を求めても「たらい回し」に遭う現状があり、孤立感を深めている。医療的ケア児支援センターの設置は、家族の精神的な支えとなり、相談窓口のワンストップ化を実現することで、孤立感を防ぐ効果が期待される。
✅ 医療的ケア児支援法は、医療的ケア児と家族の支援に特化した法律として大きな意義を持つが、施行されただけでは支援の拡充はされない。国や地方が法律の理念を具体化していくことが重要であり、地方議会での積極的な後押しも必要となる。
✅ 医療的ケア児支援センターは、家族のさまざまな悩みにワンストップで対応する「情報の集約点」となる。医療や福祉、教育・保育など、関係機関と連携することで、個々のニーズに合った適切な支援につなげることが期待される。
さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/km/tanaka-masaru-hiroshima/2021/11/09/055333/医療的ケア児支援法の施行は、大きな一歩ですが、これからが正念場ですね。
内多勝康さんは、医療的ケア児とその家族の現状について、厚労省の調査結果や自身の経験に基づいて説明しました。
調査では、家族が抱える不安や日々の生活の緊張感、外出や旅行などの活動の制限、仕事への参加の困難さなどが明らかになりました。
医療的ケア児のお母さんからは、命の危険と隣り合わせの生活、慢性的な不眠、心身の疲れ、社会からの孤立感、経済的な不安、きょうだいへの影響など、切実な声が寄せられました。
内多さんは、医療的ケア児本人だけでなく、家族全体を包括的に支援する必要性を訴え、2021年に施行された「医療的ケア児支援法」を紹介しました。
この法律は、医療的ケア児の健やかな成長と家族の離職防止を目的とし、保育・教育の拡充、医療的ケア児の支援体制整備などを盛り込んでいます。
内多さんは、この法律が社会の意識改革と医療的ケア児とその家族に対する支援体制の強化につながることを期待しています。
医療的ケア児支援法って、効果あるんかな?
医療的ケア児の社会参加と課題
医療的ケア児の社会参加は、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて不可欠です。

✅ 医療的ケアが必要な子どもは全国に1万8千人以上おり、親は深夜早朝の痰の吸引などで睡眠不足に陥り、心身ともに疲労が蓄積し、地域の中で孤立を深めてしまう。
✅ 解決策は、子育てを社会全体で支えること。家族だけで抱え込ませるのではなく、地域全体で協力することで、子育ての負担を軽減できる。
✅ 知恵と工夫次第で、医療的ケアが必要な子どもと家族が地域社会の中で安心して生活できる居場所を創出することが可能である。
さらに読む ⇒東京すくすく | 子育て世代がつながる ― 東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/message/977/内多さんのような熱意を持った人がいる限り、医療的ケア児を取り巻く課題は必ず克服できるでしょう。
元NHKアナウンサーの内多勝康さんは、医療的ケア児の医療・福祉・教育を包括的に支援する医療型短期入所施設「もみじの家」のハウスマネージャーを務めています。
内多さんは、社会福祉士の資格を取得し、医療的ケア児への支援に長年取り組んでいます。
内多さんによると、医療的ケア児は全国で約2万人おり、毎年増加しています。
家族だけで支えるには限界があり、社会全体で支援体制を整える必要性が高まっています。
医療的ケア児の社会参加は、日本の文化を大きく変える可能性を秘めている一方、教育現場での受け入れや、支援体制の整備には課題も多いとのことです。
医療的ケア児を支えるには、看護師を中心とした医療専門職の確保が不可欠ですが、人件費などの経済的負担が大きく、公的制度の充実が求められています。
また、保育士など、医療以外の専門職の報酬体系も課題として挙げられています。
内多さんは、公的な制度整備と社会全体での意識改革が、医療的ケア児が安心して地域で暮らせる社会を実現するために不可欠であると訴えています。
内多さんの活動は、医療的ケア児の社会参加を促進する重要な役割を果たすと信じています。
内多さんのような、社会に貢献したいという熱い思いを持った人たちが、未来を明るく照らしてくれるでしょう。
💡 元NHKアナウンサーの内多勝康さんは、医療的ケア児の支援に人生を捧げている。
💡 安定したキャリアを捨て、福祉の道へ転身した理由とは?
💡 医療的ケア児とその家族の現状、そして未来への希望について語ります。


